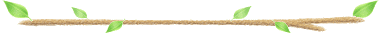
piece.07
僕らの行く先

青く輝く守護水晶を、ソロは夢見るような心地で眺めていた。守護水晶のあちこちに刻まれていた細かな傷はすっかり消え去り、滑らかに磨かれた表面は鏡のように森の枝葉を写し取っている。
薄水色の煌きを取り戻したその御神体に、ソロの過去の記憶が重なって鮮明に蘇る。自分が知る守護水晶は、元々こんな姿をしていたのではなかったか。
『よくやった! ありがとな!!』
満面の笑みを浮かべたヴェイスから、強い力で肩を叩かれる。ムジカに頭をわしわしと撫でられ、半ばもみくちゃにされながら、ソロは安心と感動からへたりこみそうになるのをどうにか堪えた。
守護水晶は癒され、ソロもよく知る神聖な輝きを取り戻した。精霊が、はっきりと告げたのだ。
「はー、よかったぁ……」
力が抜けた後、一拍遅れでソロの胸に沸き上がるのは大きな達成感。
街や人々を支える力を持った守護水晶を修復するのは、水晶調律師にしかできない仕事である。他でもない自分自身がそれを成し得たことが、嬉しかった。
精霊と、何より守護水晶そのものに、力を認めてもらえたように感じたのだ。
「おいおい、これ一つで疲れてたらこの先旅の調律師なんてできねーぞ?」
「そうですよね。ただ、ほっとしちゃって……」
明るく告げるムジカに、ソロは苦笑いを返す。ヴェイスもまた、腰に手を当てて朗らかに笑った。
『初仕事完遂ってことだな。ホント、よくやってくれたよ』
「光栄です。ご教示ありがとうございます、ヴェイス様」
演奏の途中で彼女が歌い出した時は心底驚いたが、女神の代行者たる精霊の歌声を直接耳にする機会などそうそうないのだ。考えてみれば自分はとんでもない僥倖だったのではないかと気付いて、ソロは頭を下げた。
『唄詠、でいい。昔人間につけてもらった名前なんだ』
指を立てたヴェイスから、注釈が入る。
「ウタヨミ?」
『あぁ。踊りや歌うのが得意だから、唄詠ってな。今回お前を頼ったのも、調律手段が音楽に関わる奴の方が教えやすいと思ったんだ。こいつを治してくれて、本当に感謝してるよ』
守護水晶を親指で示すと、ヴェイスはソロの頭からうとうとしている雛鳥を抱え上げた。『お前もお礼言いな』という精霊の言葉を理解したのか、雛鳥はソロに向かってピィピィと鳴く。
『さてさて、こっちとしても礼をしたいな。良いものをやろう』
「え、そんな滅相も……!」
『等価交換は人の子が決めた公平なルールだからな。恩に礼を返すのは、当然だ。おとなしく従っとけ』
「……では、ありがたく頂戴します」
確かに仕事に対して正当な報酬を受け取るのは、これから先の旅を考えても必要なことだ。ソロは納得して頷いた。
『ただちょっと、古い挨拶みたいなのがあってな。決まり文句ってヤツだから、ちょっとばかり付き合ってくれ。ほれそこ、膝着いて』
「あ、はいっ」
自らの足元を指で差し示し、軽い咳払いと共にヴェイスは表情を引き締める。片膝を着いて跪いたソロの頭に掌を載せ、精霊は厳かな声音で告げた。
『世界樹の加護のもと、春の精霊たる一柱ヴェイスが認める。ソロ・シリンクスよ。汝、正しき心を以って水晶調律師としての役割を果たすこと』
「……女神とこの大地に誓って。心に刻みます」
波紋のように広がる、心地の良い声だ。胸に手を当てて、ソロもまた静かに宣言する。
『……約束は交わされた。汝に証を授けよう』
頭を上げたソロの前にすっと差し出されたのは、小さなカフスだった。銀の輪に蜂蜜色とも向日葵色とも言えない艶のある雫型の石が装飾されており、光の加減で明るい若草色に輝く。
生命の営みに欠かせない恵みの水を象徴する雫型の石は、守護水晶を癒し、その力を保つことで人々の生活を守るという水晶調律師の役割を表していた。
『はい、これでおしまい! 面倒っちゃ面倒だけど、やっぱたまには精霊としての威厳を見せないとなぁ』
一呼吸ほどの間を置いて、ヴェイスが手を叩く。ソロはまだ受け取ったカフスをまじまじと眺めていた。精霊がくれたこの『お礼の品』は、同時にソロが最も欲したものの形でもあった。
「……この石が、水晶調律師の証ですか?」
『そう。他の精霊連中がいるとこでも、コレがあればお前がおれのお墨付きだって分かるはずだ。まぁ性格バラバラで偏屈なのもいるし、おれがよろしく言ったところで歓迎されるか確約できないのが申し訳ないんだけど』
「いいえ……いいえ。とんでもないです、最高の頂き物です……綺麗だなぁ……」
ソロは思わず、感嘆の声を漏らす。それほどまでに、感動していた。
精霊をも認める、水晶調律師としての印がこの手の中にある。証そのものを贈られるだけでなく、祝福まで授けてもらえるなんて思ってもみなかった。
受け取ったものの意味を確かめるように、ソロはカフスを両手で包み込んだ。同時に、これを授けてくれたヴェイスの期待に応えたいと強く思う。
『お前の旅に、幸多からんことを』
自分はこの石と精霊の祝福に恥じない、祖母にも精霊様にも胸を張れるような調律師になるのだ。
ヴェイスに見送られ、その掌の温度を思い出しながら、ソロはそう決意したのだった。
*
「あれ、旦那どこ行ったかと思ったら~」
街外れまで戻ってきたところで、ソロとムジカはその後ろ姿を見つけた。いつの間に祠を離れていたのか、エスパーは声をかけられて顔を上げる。
「エスパーさん、何かあったんですか?」
「……別に何も。そっちはどうなんだ、守護水晶は?」
「バッチリだぜ、なぁ?」
不意に視線を逸らしたエスパーを気にする様子もなく、ムジカはソロの肩を叩いて見せる。ソロの首元を飾るタイには、ヴェイスから受け取った雫型のカフスが光っていた。
「それは結構。あの精霊も喜んでただろうよ」
「はい。それで、エスパーさん。お話があるんです」
祠を出てここまでムジカと話したことを思い出しながら、ソロは少々不機嫌そうな顔の青年を見つめる。そして、はっきりと告げた。
「僕の旅に、付いて来て頂けませんか?」
「は?」
「僕は……旅回りの水晶調律師として、これから世界を巡るつもりです。ここだけじゃない、忘却の地にも行ってみたいと思ってます。だけど世界には魔物もたくさんいて、僕ひとりの力じゃ心もとないんです。ダメですか」
忘却の地。村を発つ前、ソロが母親に言えなかったのがこれだった。
百年近く前、フィン・マ・クルはある大災害に見舞われている。守護水晶を悪用した魔物によって負の力が蔓延・暴走し、世界の一部が引き裂かれ分断されてしまったのだ。現在において【ネバーグリーン】と呼ばれる凶事である。
またネバーグリーンで引き裂かれた大地の欠片は空間の歪みで隔たれ、「忘却の地」と名付けられた。そこには、災いを免れた地域以上に強力な魔物達がはびこっているらしい。
──もちろん本土であっても旅の危険は付きものだが、忘却の地は本来の地形や気候すら変貌してしまったような場所だという。母はソロの志す水晶調律師としての旅が、そんな危険地帯を視野に入れたものだなんて考えもしなかったんじゃないだろうか。
ソロはある理由から、どうしても忘却の地へ行きたかった。
「忘却の地……」
何か思うところがあるのか、エスパーは短く呟いて考え込むように腕を組む。ややあって、ソロを横目で見た。
「俺は運び屋であって用心棒じゃない。それに、慈善事業でやってるわけでもないしな」
言われてみれば、エスパーの言は尤もである。彼には彼の仕事があって、無理強いはできない。しかし、まだ交渉の余地はあった。
「依頼内容は……、【僕を世界各地に運ぶこと】です。運び屋さん、なんですよね?」
ソロは運び屋である彼の説得に当たり、酒場で給仕に聞いた話を思い出す。確かエスパーの仕事は、依頼とその報酬に応じて何でも運ぶ対象になり得るのではなかったか。
少々屁理屈を交えてはいるが、噂が本当ならこちらの提案と彼の勘定次第で、生きた人間を運ばせる……つまり道中の護衛として力を借りることができるかもしれない、と考えたのだ。
「お礼に関しては旅周りで得る路銀、調律などの成果報酬を山分けという形でどうですか」
「……報酬ねぇ」
先程からおうむ返しばかりで、エスパーはなかなかそれらしい反応を見せない。ぐっと挑むように青年を見つめながら、ソロは内心でたじろいだ。
相手が渋るのも当然と言えば当然なのだ。この依頼には、本来定めるべき期限やはっきりした目的地がない。報酬の件も少し考えれば、分け前など旅仲間に対するごく普通のやり取りの範疇だと気付くだろう。
やはり自分の依頼は、あまりに稚拙すぎるのだろうか。
「旦那、頼むよ」
そこで、ムジカが進み出て口を開いた。
忘却の地を含めて旅をしたいとソロが相談した時、彼を引き入れるべきだと最初に勧めてきたのはムジカだ。 エスパーは旅慣れている上に強力な魔術師であり、何より信頼に足る人物なのだという。
ソロもエスパーの魔法の威力は街で目にしているし、戦力として心強いと思うからこそ、ムジカの勧めに従って彼に声をかけてみようと決めたのだ。
「気難しい所はあるが、嘘吐かねぇしな。旅の道連れとして護衛を頼むならあんただって、俺がソロに旦那を推したんだ」
「気難しい、は余計だ。俺を買いすぎじゃないのか?」
「あんたがいなきゃ、俺は今ここにいねぇよ。買って何が悪い? それにコレは、あんたにも充分利がある交渉のはずだ。いつまでもここらに留まってるつもりもねぇだろ? 脈ナシって最初から切り捨てるなら、わざわざこうして俺達を待ってた理由、聞いてもいいかい」
ムジカとエスパーの間に、何とも言えない緊張した空気が流れる。
この二人の過去に、一体どんなことがあったのだろうか。とても気になるのだが、会話に割って入ってまで事情を聞くのも場違いに思えて、ソロはただムジカの説得がどうなるか見ていることしかできない。
「昔から強引だな、お前は」
「性分でね。旦那の時間を、コイツに分けちゃくれねぇか」
エスパーは真剣な表情で返事を待つ親子を見比べた後、考えを巡らせるように目を閉じる。やがて根負けしたように、やれやれと肩を竦めた。
「……仕方ないな。引き受けてやる」