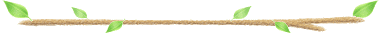
piece.06
精霊と繋ぐ旋律

ソロは父の紹介を聞きながら、突然目の前に現れた少女に見入っていた。
陽光を透かして白い艶を帯びるヴェールが、ふんわりと風に靡く。肩が出る形の真っ白なドレスは、白に合う淡い色合いのドレープに花飾りやリボンで飾られていて、まるで花嫁か歌姫が着る衣装のようだ。向日葵色の髪を腰まで伸ばしており、つり上がった菫色の瞳は猫を連想させた。
絹擦れの音さえ立てずに突然現れたことや、本人の佇まいからもどこか人間離れした雰囲気を感じさせる。不思議な空気を纏う少女だった。
ソロが魂を抜かれたように少女の頭から足元までを眺めていると、足元に広がる下生えのあちこちから、彼女を中心として小花の蕾がぽつぽつ開いていくのが目に入る。まるで植物達が喜んでいるようだ。
父の言う通り、彼女は本物の精霊なのだろう。
『遅ェよムジカ! いつまで待たせてんだっつーの!』
しかし直後、同じ人物から放たれた悪態にソロは別の驚きで固まってしまった。
「……はい?」
今の台詞を発したのは、腰に手を当てた仁王立ちで目を尖らせているこの少女か。
そういえば彼女が現れる直前にも、似たような口調の同じ声を聞いた気がする。判断材料は得ていたはずなのに、見惚れてすっかり忘れていたのだ。
「えぇと、僕はソロといいます。初めまして……父がお世話になって、ます?」
『あぁ、話にゃ聞いてるよ。お前、水晶調律師を目指してるんだってな』
我に帰って挨拶すると、想像よりもずっと気易い返事が帰ってきた。なまじ声が澄んでおり耳通りが良いものだから、砕けた言動との差異に戸惑ってしまう。
精霊はフィン・マ・クルの地を創った女神から力を受け継ぎ、今も彼女の目として永い時を見守っているという世界の守護者達だ。彼らが生まれ出る母胎となった樹は世界の暦として広く知られ、中でも【樺のヴェイス】は春の始まりを告げる精霊として、ホルンの街では特に親しまれていた。
そんな信仰対象となる存在と、目の前にいる少女の人物像がソロの中でうまく結びつかない。一言二言喋っただけなのに、かなり人間じみているような気がする。
「何だよソロ、どうしたってんだ」
「いえ、……習ってたよりも、ずいぶん大らかな印象の方だなって……」
『まぁ、驚くのも分かるが。ムジカ、言っとくがお前みたいに躊躇なく口説いてくる方が少数なんだからな』
さらっととんでもないことを暴露した精霊に、ソロは途端真っ青になってムジカの襟首を掴んだ。
「よりによって精霊様に何てことしてるんですか、バカなんですか!? それともお母さんに殺されたいんですか!?」
「んなこと言っても、まだエトに逢ってすらいなかった頃の話だしなー。ヴェイス様が精霊だってのも最初知らなかったし」
「馬鹿は馬鹿だ」
無礼を働いたらしい当のムジカは、息子の慌てぶりもエスパーからの冷ややかな視線もどこ吹く風といった調子だ。この人はどうしてこうもいい加減なのだろう。
相手にとんでもない迷惑をかけていたのだと知り、ソロは青ざめたまま必死に頭を下げた。
「父がすいません、本当にすいません」
『別に今じゃ気にしてねぇさ、お供えものも貰ったし。そんなことより守護水晶だ』
ヴェイスはドレスの裾を靡かせながら、御神木に歩み寄る。ソロも改めて守護水晶に向き直った。
『水晶調律師ってひとくちに言っても、人によって守護水晶の修復手段は色々あってな。お前、何を使うつもりだ?』
「これです。音楽を奏でて、守護水晶を【癒す】って……祖母から、そう習いました」
ヴェイスの問いに、ソロは腰元のベルトに吊ったホルダーから横笛を取り出した。白樺の木から作られた横笛には小花と蔓草の飾り模様が彫られており、触り心地は磨いた石にも似てすべすべしている。
祖母はいつも楽器を手入れした後に、音色の調整を兼ねて様々な曲を吹いてくれた。祖母の奏でる曲、この笛の音が、ソロは小さい頃から大好きだった。
「修復手段に関しては一通り習ったんですが、何を演奏すれば?」
祖母はこと音楽や守護水晶に関してソロに知識を授けてくれたが、肝心の曲や演奏の技巧についてはほぼまったく教えてくれなかった。ソロは祖母の見よう見まねに加えて、街で買った楽譜を使って独学で演奏を練習したのだ。
『そう。音楽で守護水晶を癒すなら、知っておかなきゃいけねぇのは曲なんだ』
普通の演奏で人や場所に合わせて曲を選ぶことがあるように、守護水晶を癒すのにも相応しい楽曲がある。やはり、何でもいいというわけではないらしい。
『守護水晶っていうのは、その土地土地に根ざすものだからな。音楽で治そうっていうんなら、よく聴く音楽を聴かせてやるのが一番いいだろう。思いつくものを吹いてみろよ、間違ってもフォローはしてやる』
「えぇっ?」
精霊から、まさかのアドリブ要求。唐突なお題に、ソロはひどく戸惑った。
知恵を求めるように周りに立つ大人を見回して、エスパーと目が合う。しかしエスパーはソロの視線を受けて腕を組み、首を傾げた。
「俺はよそ者だし、こういう分野に明るくもない。あんたの方がよっぽど詳しいはずだろ」
「あ、はい。すいません、無茶言って」
やはり、エスパーはこの辺りの土地に住む人間ではないらしい。
初めての調律にも関わらずこの漠然とした難題に、不安が黒雲となってソロの胸中に広がる。
しかし自分は見習いとはいえ、立派な水晶調律師なのだ。憧れ続けた職業に対して、いい加減な態度で挑むわけにはいかない。
一度頭を振って、考える。今日初めて調律を行うような見習いであり、正式な水晶調律師ではないソロが呼ばれた理由は何なのか。
最初自分に声をかけてきたのはいい加減なムジカだが、精霊のヴェイスは一切異を唱えていない。問われたのは調律の手段だけで、改めて腕前に言及されることはなかった。
つまりヴェイス自身、ソロという人選に対しては納得しているということになる。
いくら分母の数が少ないとはいえ、腕利きの水晶調律師は他にも沢山いるのだ。まさか世の秩序を守る精霊が、大事な守護水晶を癒すための職人を「知り合いの息子だから」などという理由だけで選ぶわけもない。
となると、今回必要とされているのは歌なり演奏なりの「音楽」を媒体とする調律師で、技術の卓越具合はそこまで重要視されていないのかもしれない。
守護水晶は土地に根ざすものだと、ヴェイスも言っていたではないか。おそらく大事なのは、この場所をよく知っている人間であることなのだ。
そして自分が習得した中で、ヴェイスの言うように「よく聴く」……このホルンの街に、馴染んだ曲。それは何だろうか。
「……そうだ」
ふと視線を上げ、頭の片隅に閃いたイメージに従ってソロは笛を口元に当てる。そっと息を吹き込んだ。
素朴な笛の音色が、辺りに響いた。春風に流れていく音を聴きながら、ヴェイスが心地よさそうに目を閉じる。
題は、【君を待つ風】。ホルンの街の教会で昔からよく歌われ、演奏される古語の曲だった。
元々はシェラ鳥への信仰から生まれたもので、雛が巣立つ時の羽ばたきを子供達の明るい未来に重ねている、と日曜学校で習った記憶がある。
曲を連想するきっかけになった雛鳥は、大人しくソロの頭の上に乗ったままだ。ピィ、ピィと鳴く声が心なしか嬉しそうに聞こえる。
やがてソロの奏でる音の響きに共鳴するように、風がきらきらと光を帯び始めた。大気に漂う魔力が、音色に反応しているのだ。
『……いい音だな』
目を細めて演奏の様子を見ていたヴェイスが、一歩踏み出す。軽やかに舞いながら、音に合わせて歌い出した。
ソロの笛の音に、透明で澄んだ歌声が重なる。精霊の舞う軌跡を辿るように、あちこちの下生えから蕾が花開いていった。
「(え!?)」
まさか精霊が同調して踊り出すなどとは思いもよらず、歌声に目を開いたソロはぎょっとして演奏を止めそうになる。目だけを動かすと、ムジカが無言で『続けろ』という指示を出していたためどうにか音を外さずに済んだ。
より集まった青い光の粒子が帯のように重なり、連なって守護水晶にまといつく。守護水晶を包み込んだ光は呼吸のように淡く明滅し、曲の終わりと同時にほの白い煌きを放って消えた。
「……どう、でしょうか?」
横笛から唇を離し、ソロは深く息を吐いた。とても緊張したが、音を間違えず吹けたことには心底ほっとしていた。後は調律がうまくいったのかどうかだ。
演奏が終わってすぐに、守護水晶に触れてあちこちを覗き込んでいるヴェイスの様子も気になる。何となく結果を知るのが恐ろしいような気持ちで近付くと、守護水晶が強く輝いた。
「うわっ!?」
強烈な光に、精霊以外の全員が反射で目を閉じる。
やがて瞼の裏に届くまでの輝きが収まり、ソロが目を開くと。
静かに、しかし、まるで自らの輝きを誇るように青い煌めきを放つ守護水晶があった。