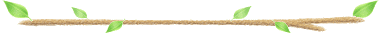
piece.05
加護の下で生きる人々

「……で、これはどういうことなのか。説明して頂けますよね」
母親似の顔に眉根を寄せ、ソロはムジカの前に掌を突き出した。
少年の掌にちょこんと鎮座しているのは、シェラという鳥の雛だ。青い羽毛に覆われた、ソロの掌にもおさまるほどの小さな身体はふかふかしていて、触っていて気持ち良い。
シェラは妖精族と相性が良く、エポナ村やホルンの街では「空の御使い」、あるいは「精霊の友」と呼ばれる神聖な生き物だという。春の空を写し取ったような色の羽は厄除けや幸福を呼ぶお守りとして重宝され、ソロの髪飾りもその羽を用いて作られた品だった。
しかしここにいる雛は生まれて間もなく、自らの翼で飛ぶことも叶わない状態だ。それが怪物に変化してしまった経緯とは、どのようなものなのだろうか。
「おー可愛い可愛い……、で? 何だって?」
「人の話を聞け、馬鹿」
雛鳥の身体をソロの頭に載せて喜んでいたムジカは、青年にひっぱたかれてようやく二人の方を見た。ソロと青年、どちらからともなく溜息が零れる。
──この父親は、まったく。
全く話が通じていない気がして、少し呆れてしまう。ソロは頭上で大人しくなった雛鳥を撫でながら、ムジカに何から聞くべきかを考えた。
「この子、さっきの魔物の正体ですよね。なんであんなことに?」
「お前、理由に心当たりがあるんじゃないのか」
ソロに同調してか、青年もまた頭痛を堪えるような声音で助け舟を出してくれる。
「あぁ、あるよ。そのことも合わせて、ソロに頼みたい仕事があるんだが……丁度いいから旦那も付いて来てくれや」
何が丁度いいのか、ムジカはそう頷くなり踵を返してすたすたと歩き出した。来れば分かる、と言わんばかりだ。
ムジカは細工師の仕事に対してとても真摯だが、こと日常生活においてはマイペースであり、人の話を聞かない所が多々ある。日頃の言動を見習うならば父ではなく母の方にしよう、とソロは心に決めていた。
一芸に秀でた天才には変わり者が多いというけれど、父親もそんな一人であるらしい。
「僕、ソロといいます。改めて、さっきは助けて頂いてありがとうございました」
そういえばと思い出して、ソロは前を歩く父親を追いながら青年に声をかける。
先頭を行くムジカが立ち止まろうとしないので、必然的にソロの自己紹介も歩きながらという忙しいものになる。青年はソロの挨拶に振り返り、青とも緑とも取れない不思議な色の目を一度瞬くと、
「……エスパー、だ」
「変な名前だろ? 運び屋やってていろんな土地を巡ってるんだとさ、俺もずいぶん前に世話になったよ」
「悪かったな、【変な名前】で」
笑いながら合いの手を挟むムジカに、エスパーはフンと鼻を鳴らす。彼が運び屋だという話は酒場で聞いていたが、父親にこんな友人がいたとは知らなかった。
「お仕事で扱う荷物としてはどんな……、どうかしました?」
「……あんた、父親に似てないって言われるだろ」
変な名前だと言われたのが癪だったのか、皮肉を含んだ台詞にソロは苦笑いする。いくら大らかな人だとはいえ、父の手前「自分でもそう思います」なんて頷くには気が引けた。
だがソロとしても、エスパーを見ていて少々気になることがある。
おおよそ二十歳前後であろうこの青年が、倍近く年齢差があるムジカの頭を平気で叩いていたり、本人から「旦那」と呼ばれていることに対して、妙な違和感を覚えたのだ。
父の言語能力が怪しいのは今に始まったことではないし、重々承知もしている。
だが、これではまるで──
「ところで、一体どこへ向かっている?」
ソロの思考は、これもまた気になっていた内容の質問を耳にしたことで中断される。
「今回の事件発生現場、かね。守護水晶がある祠、ソロは知ってるだろ? こればっかは実物の状態見せないと説明し辛いからなぁ」
暴れ回っていた魔物が消えたことで、人々は徐々に平静を取り戻し始めたらしい。ムジカは乱雑に散らばった木箱や露店の片付け、周囲の被害状況を確かめている人々に逐一声をかけながら、その間を縫って歩いて行く。
「すいません、僕がもっと頼りになればこんな風には……」
「さっきも言ったろ。人さえ無事ならこれくらい何とでもなるんだよ、お前と旦那がいなきゃもっとひどかったんだから」
ふと顔を上げ、ソロは父親の背中を見つめる。ムジカが首を巡らせてソロを振り返り、歯を見せて笑った。
「俺の息子が、俺の作った杖で街を守ったんだ。これ以上嬉しいことはないぜ」
何となく責任を感じて沈んでいた心が、徐々に軽くなる。彼の表情は確かにソロの父親であり、何よりも心強くて胸が暖かくなった。
「……お前、その態度の落差はどうにかならないのか」
「旦那は失礼だな、俺は普段からよき父親であるように務めてるってのにさ。なぁソロ?」
「素直に感動させてくださいよ……」
やっぱり気のせいだったかも、などと考えながら、それでもソロは職人が作った自慢の杖をしっかり握りしめていた。
しばらく歩くと並び立つ家屋が途切れ、街外れの森道へと入った。
ホルンの街の守護水晶は、象牙で造られた小さな祠に御神木として祀られている。森で最も樹齢を重ねた樹の中腹に、一抱えもある卵型の水晶がまるで抱かれているかのような形で埋もれているのだ。
天然の祭壇に祀られた水晶からは、今はばちばちと火花のように赤い光が散っていた。
「あれ……水晶ですよね?」
久々に目にする守護水晶に、しかしソロは怪訝な顔になった。石が放つ煌めきが、どこか不穏なものに見えたのだ。
「……守護水晶って、こんな刺激的な光り方をするものでしたっけ」
ソロの知る──少なくとも、この街にある──守護水晶は通常、ほんのりと透き通るような水色に輝いていたはずだ。ソロ自身は日中にしか見たことはないが、話によれば夕暮れ時や月夜などの時間帯に応じて淡く光の色合いを変える、とても美しい石だという。
「分かるか? 何か、知らんうちに老朽化が進んでたみたいでなぁ……ちょっと来い」
答えるムジカの目は真剣だ。守護水晶を間近で眺め、ソロを呼び寄せた。
「近くで見ると、思ったより細かい傷が多いだろ」
「はい……しかもここ、こんなにはっきり……」
ソロはムジカに促されるまま、輝く宝石をまじまじと観察する。よく見れば守護水晶は傷だらけで、ほんの僅かに欠けた形跡もある。消耗した守護水晶では、その能力を十分に発揮できないのも当然だった。
魔物を創り出し育むのは、強く寄り固まった生き物の負の感情である。その具現化を制御し、脅威から人々を守る守護水晶の力は、ある程度有限のものなのだという。
ソロは敬愛する祖母から、寝物語に何度もそんな話を聞いた。
そして人々を守る水晶の力を維持するため、定期的に守護水晶を点検・修繕する役目を担った職人が、水晶調律師だ。
彼らがいなければ守護水晶の力は時間と共に綻び、石そのものが壊れてしまう。守護水晶が壊れて結界の加護を失えば、人里はあっという間に魔物の餌食となってしまうだろう。
「……いつから放置されていた? むしろよくここまで保ったな」
「確かに。田舎だからかね? 専門職が街を通ることはあっても、ここに寄るかまでは個人の性格次第だしな……」
ムジカはそこで言葉を切る。ソロも考えること少し、表情を陰らせた。
「……街の人も誰も、守護水晶がこうなってるのに気付かなかったってことですか?」
人の出入りが多い場所とはいえ、ホルンの街は田舎だ。人々の感情の波も穏やかであり、基本的に変化が少ない。だからこそ、水晶の異変に気付くのが遅れたと言えるのかも知れない。
「結界を張ってるモノに、いつでも自由に近付けると? いくら何でもまずいと思うがな」
「祠へのお参りはいつでもできますけど、守護水晶を直接見られるのは季節ごとのお祭りの時だけなので大丈夫です。ただ……、その分春の祝祭では、街の内外から結構な人がお参りに来てたと思うんですよ」
この街の守護水晶がどう扱われているのかを知らないエスパーに、ソロは首を横に振った。
あるいは祝祭の時に見た参拝者が誰も気付かなかったのなら、守護水晶がこの状態に入ったのは本当にここ二、三日の間ということになるのか。
水晶の傷は注意して見なければ分からないほどのものだが、わずかでも欠損が出るまでに損傷しているとなれば、いつまた先程の怪鳥のような魔物が現れるか分からない。
「この子が変異した原因は、守護水晶に関係が? 飲んじまった、とか何とか言ってましたけど」
「そう。水晶の欠片を、雛が誤飲しちまったのさ。普通なら守護水晶の欠片なんか飲んだって、精々大きくなる程度で化け物になったりはしないはずだ。欠片は糞に混じって地に帰る」
ムジカはそう言うと、小指の爪ほどの水晶の欠片をつまんで見せた。
「巨大化も異常だがな。そもそも手入れが行き届いていれば、コレが欠け落ちることもないだろ。それに……」
依然赤い光を放っている守護水晶に目を向け、エスパーが何か言いかけて口を閉じる。
負の力は、時間をかけて少しずつ守護水晶に蓄積している。この雛鳥は守護水晶の汚れた部分を吸収し、凶暴化してしまったのだ。
「……ごめんね、辛い思いさせたね」
もう一度頭上でうずくまった雛を撫でながら、ソロは眉を下げる。応えるような「ピィ」という鳴き声が聞こえた。
「お前、村からそのまま来たんだろ? 初仕事だ、コレの修繕やってくれねぇか」
「はい!」
ムジカからの本題に、ソロは一も二もなく頷いて見せる。そのために自分が呼ばれたのだと、今までの話で理解していた。再びこの雛鳥のような被害を出す訳にはいかない。
『やーっと来たか! 待ってたんだぜ!』
エスパーでもムジカでもない誰かの声が聞こえて、ソロは首を傾げた。木々の枝葉が風もないのに揺れ、軽やかな鈴の音と共に人影のようなものが頭上から近付いてくる。
やがて音もなく三人の前に降り立ったのは、白いドレスとヴェールを纏う金髪の少女だった。
「ソロ。いいか? この方はな……」
とっておきの秘密を打ち明けるような顔で告げた父親に、ソロは空色の目をまん丸に見開く。
「春を司る精霊の御一人。カバの樹のヴェイス様だよ」