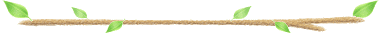
piece.04
煌めく音

「マーチ君!」
泣きじゃくっている子供を視界に捉えた瞬間、ソロは自分でも驚くような速さで飛び出していた。その身体を抱きかかえ、半ば覆い被さる形で魔物の視界から庇う。見知った子供の怯え震える姿は、いつもよりずっと小さく感じられた。
「えっ……ソロちん?」
「動かないで!」
うろたえる子供を鋭く制する。日頃から街中をよく駆け回っているわんぱく小僧だが、その両目には大粒の涙が溜まっていた。
彼はまだ、あの魔物と目を合わせていない。この子の顔を、敵に認識させてはいけないのだ。
背に受ける突風で、魔物がこちらに向かって来ていることがありありと分かった。腕の中の子供を守らなければならない正義感と覚悟、恐怖がないまぜになって、抱く腕にいっそう力が入る。
その時だった。
≪la di'nse er seln.≫
流麗な韻を伴った言葉の羅列が、ソロの耳に届く。
≪fino, bati-us guoit.≫
まるで旋律のような詠唱。自分には言葉の意味がさっぱり分からないが、綺麗な声だと、緊迫した状況の中でもそんなことを思う。
『焼き払え!!』
短く発せられた──これもまたソロには理解できない──命令と共に、ハープを思わせる音が響く。直後、背後で赤い光が爆発した。
何かが爆ぜる音と、苦鳴を上げる魔物の咆哮が空気を震わせる。熱を孕んだ風が吹きつけてきて目を瞑ったが、背中を押されたソロはつんのめって転がった。
「うわわわ……っ」
肉の焼ける、焦げ臭い匂いが鼻につく。はっとして振り返ると、自分達二人を庇うように先程の青年が割って入った所だった。魔物は悶え、自らの両翼に浴びた炎を振り払いながら青年を睨んでいる。
しかし苦しむ魔物が派手に散らす火の粉は、空気中でさぁっとかき消えていった。そのまま周囲の家屋や道端に落ちて燃え続ける様子はなく、まるで“攻撃すべき対象”とそうでないものを理解しているかのようだ。
それは紛れもない、魔法の力。青年が何かしらの手段で炎の魔法を放ったのだと知り、ソロは苦しそうな魔物と青年の姿を見比べた。しきりに首を振る魔物の様子を見て、今がチャンスだと頭の片隅に閃く。
「今なら大丈夫だから、ここから離れて。安全なところに隠れるんだ。できるね?」
驚きに声も出せず固まっている子供に、耳元で囁いた。
今の怪鳥の意識は完全に青年一人に向いているし、酷い火傷の痛みからか視線もあちこち泳いでいる。はっきりと狙いをつけ、照準を定めておくこともできない程に。
「ソロちんは?」
「僕は平気だよ、味方もいるし」
すぐ右手の路地を示しながら、元気付けるように子供の背をぽんぽんと叩く。ソロの声に子供は顔を上げ、やっと頷いた。ソロの身体を壁代わりに、素早く路地へと潜り込む。それを見送ってほっと息を吐くと、ソロは青年の隣に走った。
「ガキは行ったか」
「はい、もう大丈夫です」
横目に青年を見ながら、ソロは改めてナイフを握り直す。未だもぞもぞと動き抵抗の意を見せる魔物に、青年が目を眇めた。
「チッ、まだトドメには足りないか……面倒だな」
広げた掌からぽとりと落とされたのは、黒ずんでひび割れた小石だ。わけが分からなくて、ソロは首を傾げる。青年は再度銃を構え、ソロに問うた。
「おい、……アイツの急所、分かるか」
「……えぇと……」
頭の中の書物の知識を漁るのに、少し時間が必要だった。だが、そんなことをしなくても──
「さっきの魔法みたいなのって、また使えないんですか?」
最初は、戦力としてソロが加わることを渋っていた彼のことだ。元々、一人でも魔物に勝てる算段があったのかもしれない。
現に魔物はこうして弱っているし、まして青年が今しがた放ったような強力な魔法を使えるのなら、このまま再生の暇すら与えずにとどめを刺せそうなものなのだが。
「……弾切れだ」
「弾?」
むくりと起き上がった魔物が、ばさりと翼を広げた。
「行かせるか!」
早くも傷の再生が始まっているのか、今一度飛び立たんとする怪物の両目にすかさず青年が銃弾を撃ち込んだ。耳鳴りがするほどの音量で、怒声にも似た悲鳴が上がる。
魔物を注意深く観察しながら、ソロは頭の中の知識を総動員させた。考えろ、考えろ、考えろ──
注意深く怪鳥の様子を見ていると、その眉間に盛り上がっている瘤のようなものに気付いた。
あれは、何だ?
「……水晶?」
あの魔物独自の特徴は、額に浮かぶ記号のような紋様だ。だが実際に鉱物のような瘤があるというのは、本でも見たことがない。
しかし考え込んでいる時間はない。瘤があろうが無かろうが、眉間の部分が高い確率で急所であることに違いはないのだから。
「お兄さん!」
さっと額を指差したソロの指示を号令にしたように、銃弾が放たれる。続けて、三発。
すると──
「えっ!?」
「なっ……!?」
少年と青年が、同時に目を剥く。まっすぐに額を狙った弾丸は、魔物に命中する寸前ですぅっと消えてしまったのだ。まるで接触しようとした異物を拒絶するかのように、魔物の額にある瘤が淡い光を放つ。
敵の治癒力は別としても、両目や翼など、他の箇所を狙った攻撃は全て当たっていたのだ。にも関わらず、ここに来て何故こんな現象が発生するのだろう。
このままではらちが明かない。青年の魔法で負わせた火傷が回復しきらない内に対処しなければ。どうすればいい?
「ソロ、これ使え!!」
「あいたっ!」
よく知る声が聞こえた直後、後ろ頭にスコンと小気味よい音を立てて何かがぶつかった。
否、ぶつかったというより一点を突かれたような気がする。ソロが頭を擦りながら足元に転がったものを見ると、それは一本の杖だった。
ほっそりとした長く青い杖の先には金の装飾が施され、首をもたげたようにくるりと曲線を描く樫の枝を戴いている。更にその先端に、ひし形の水晶が吊り下がっていた。揺れる水晶はほんのりと光を放っており、ソロの顔を薄水色に照らす。
エポナ村でも精霊の象徴として祀られている、水晶樫を加工した杖だった。初めて触れるのに、細身の杖はソロの手にしっくりと馴染む。目を丸くし、少年は声の主を見遣った。
「え、お父さん!?」
唐突な闖入者。癖のある撥ねた茶髪を揺らしてソロの肩を豪快に叩いたのは、じき四十歳に届こうかというソロの父親。ホルンでも名の知れた職人──ムジカだ。
「アイツ、守護水晶を呑んじまったんだよ。その杖で叩けば、水晶を弾き出せるはずなんだ」
「あぁ、あの額にあるのが守護水晶なんですね。道理で変な瘤だなぁと……って、そうじゃなくて!」
さらりと重要なことを耳にして、ソロはムジカの方に向き直る。あっさりしすぎているこの父親に対して、聞きたいことがありすぎた。
あの魔物が守護水晶を、呑んだ?
「第一そこが問題ですよ。まず何で、然るべき場所に守護水晶があるのに魔物が入って来るんですか!?」
「あー、それは……」
「おい、質疑応答は後にしろ!」
油断なく身構え魔物を牽制していた青年の喝に、ムジカがぱっと笑顔になった。
「おっ、旦那じゃん。いいとこに来たなぁ、見てろよ俺の作った杖の実力。ほれソロ、いっちょやってやれ」
「暢気だなお前は」
「経験者の余裕ってやつさぁ。これくらいの被害、人さえ無事ならどうとでもなるっつの」
この大人達は、どうやら知人同士らしい。ソロが少々気後れしていると、父親にずいと身体を押し出された。
「時間ないんだってよ、話は後で後で」
さっきまで悠長にぺらぺら喋っていた人間が何を言うのか。ソロはうろんげな目つきでムジカを睨む。
「……本当にこれで叩けばいいんですね?」
「何だよ、俺の職人としての腕が信用できないって?」
自慢げに推すのは息子ではなく、杖の実力なのか。それにまず、この緊急事態においてそんな軽口を叩いていられる神経が分からない──などとは言わないでおいた。この父親は日頃からこんな調子で、今更緊迫した様子を見せられても反応に困ってしまいそうだ。
「……今回の報酬は、チャラだな」
どこか愚痴のような言葉を漏らしながら、両手に違う拳銃を握った青年が次々と魔物に弾丸を撃ち込む。目顔で促され、ソロは走った。
「腰入れろ、ソロ!!」
「やぁあああああっ!!」
動きを封じられて悶える怪鳥の眉間に、振り上げた杖を思いっきり叩きつける。
瞬間。
杖と魔物の額、二つの水晶の間で青い光が交錯し、視界が白く染まった。