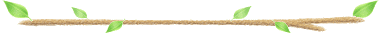
piece.03
少年と青年と魔物

青年が引き金を引くと同時に、轟音が響き渡る。白目を剥いてばったりと倒れた男を前にして、静寂が店内を覆った。
「……な、何を……」
唐突な決着を見ていたソロは、思わず息を飲む。驚愕と混乱に表情を引き攣らせたまま、眉ひとつ動かさない青年の顔を見上げた。
「何をしてるんですかっっ!!?」
我に返ると恐慌から震える身体を叱咤して立ち上がり、きっと青年を睨みつけた。青年はソロが巻き込まれたことに腹を立てていたように見えたが、ここまでするとは思ってもみなかった。
得体の知れない武器によって、公衆の面前で人が傷付けられた。いや、撃たれた場所を考えれば即死だ。そんな中で、彼に対する感謝などできようはずもない。
だが掴みかからんばかりに激昂する少年に、青年は小さく舌打ちする。面倒だとでも言いたげな視線でソロを見ると、横目に倒れた大男を顎で示した。
「馬鹿か、よく見ろ。寝てるだけだ」
「……えっ?」
目を丸くして、大男に向き直る。おそるおそる膝を着いて覗き込めば、確かに呼気もあり、額には出血はおろか弾痕すらない。強く銃口を押しつけられた痕がほんのわずかに赤くなっていたが、それだけだ。
これは一体どういうことだ。ソロが目を丸くしていると、青年がつま先で男の腹を軽く蹴った。
「……テスト用に入れてた音響弾。勘違いしたコイツが勝手に伸びたんだ。誰がこんな奴相手に貴重な実弾使うか」
「──ご、ごめんなさい!」
紛らわしい行動だったとはいえ、自分はとんでもない誤解をしていたらしい。ソロはすぐに頭を下げたが、相手から返事はない。
そっと頭を上げると、青年もソロを見ていた。何か訝るように目を細める。
「……君は、」
しかし青年はすぐに口を閉ざし、何事もなかったかのようにソロの腕を振り解いた。懐を探ると、ノース銀貨を二枚カウンターに置く。律義なことに、サズに支払っていたリフ銅貨の山はそのままだ。
「邪魔して悪かった」
厨房の奥に立つ主人にそう断ると、自分を注視する客達を一顧だにせず店を出て行ってしまった。
「ソロ坊、大丈夫だった?」
ゆっくりと喧騒を取り戻す店内で、先程まで青年を目で追っていたソロは主人の声に振り返る。
この酒場の主人は寡黙かつかなりのマイペースで、大抵客同士のトラブルには無関心と傍観を貫いている。対処に回っているのはいつも給仕だ。現にあれだけの騒ぎがあった今も、どこ吹く風でシチューの鍋をかき回していた。
「あぁ、はい」
「何にしても喧嘩はいただけないや。リィサ、あの人今度来た時に“次同じことしたら追い出す”って伝えてくれる? ……サズは店から叩き出しといて」
あくまで鍋から目を離さず、主人は早口に告げるとそれきり黙り込んだ。
「今のお兄さんって、よくこの店にいらっしゃるんですか?」
ふと気になり、ソロは手際良くテーブルの上を片付けている給仕に声をかける。彼女はお喋りが好きで、聞けば小耳にはさんだ噂など色々な話を教えてくれるのだ。
少年の何気ない質問に、給仕は少し逡巡してから首を横に振った。
「最近街に来た人みたい、顔を出したのは今日で二回目かな。運び屋をやってるって話だけど」
「……運び屋? というのは……」
耳慣れない職業だった。しかし、仕事の内容をまったく想像できないというわけでもない。一体どんなものなのだろう。
「名前の通り、依頼に応じて何でも運んでくれるんだって。聞く限り、便利屋に近いのかな? しかも、相当腕利きらしいし……でもあの人、他にも変な噂があってね……」
「……変な噂?」
急に声を落とした給仕に、ソロもまた囁くように聞き返す。店の外から鳥の声と、木片が砕けるような音が聞こえて来たのはその時だった。
物音は少し遠く、聞こえたのは耳の良いソロだけかもしれなかった。
「……ん?」
直後、今度は銃声が響く。音は先程よりも明らかに近かった。
流石にソロ以外の客達も何ごとかと騒ぎ始め、窓から外を見た客が悲鳴を上げた。
「ヒィ! 魔物……ッ、魔物が暴れてるうううう!!」
その言葉に、ソロもはっと窓に貼りつく。やがて驚きに声すら出せなくなった。
外では、巨大な鳥が暴れていた。時折飛来して翼をはためかせては、何かを避けるように空へと逃れる。その繰り返しだ。
あれが一体何をしているのかは分からない。だが奇怪な鳴き声を上げて飛び回る化物の姿は、酒場の客達を恐慌状態に陥れるには充分だった。ある者は青ざめて縮こまり、ある者は喚き立てている。自分のすべきことを心得ている給仕は、自分も顔色を悪くしながら大人達を宥めるのに必死だ。
銃声から先程の青年を連想し、ソロは心配になって小さく扉を開く。発砲音からして、外にいる鳥と戦っているのが彼ではないかと思ったのだ。
案の定、ソロの前に青年の背中が後退して来て扉を塞ぐようにぶつかった。
「馬鹿、出てくるな!」
扉の隙間から見れば、魔物の姿はよりいっそう大きく見えた。身体は胴から翼にかけて白と黒の羽毛に覆われており、甲高い声を上げて地上に立つ青年を威嚇している。
逃げ惑う通行人達から引き離すように距離を取って、青年は魔物と戦っているのだ。
刹那、魔物が確かにソロを睨んだ。僅かに足が竦み、ソロの背筋に悪寒が走る。
このままでは、いけない。
「お兄さんこそ、大丈夫なんですか!?」
銃に弾丸を詰めている青年の隙を縫って、ソロは店の外へと滑り出た。
青年の忠告を聞かずに出たのは、咄嗟の行動だった。
大きさは少々規格外だが、あの魔物には見覚えがある。知識としても頭に入っていて、弱点も知っていた。そして何より、さっきの一瞬で既に自分が敵の標的に含まれたことを悟ったのだ。
この魔物は、獲物と見なした相手を執拗に追う習性がある。 怪鳥の視線は青年と一緒に間違いなくソロをも捕らえていて、血走った目が鋭く光っていた。
「中にいろ、邪魔だ!」
青年が鋭く言い放つ。次いで撃ち出した弾は怪鳥の左翼を貫き、絶叫が辺りに轟いた。
「もう無理ですよ、僕までしっかり獲物認定されちゃいましたから!」
「は!?」
ソロは言いながら荷物袋に手を突っ込むと、削り出し用のナイフを取り出す。武器としては、ないよりマシといった程度だ。邪魔だの店に戻れだのと言う青年の言葉は尤もだが、襲撃対象に加えられてしまった以上、自分が下手に逃げ回れば周囲に被害を広げる可能性がある。
しかし、何故こんな街中で魔物が暴れているのかがそもそも分からない。
凶暴な魔物達の脅威から身を守るため、人里には【守護水晶】という石が置かれている。その聖なる力によって守られている場所に、悪しき魔物は決して近付けない──はずなのだ。
それは無論、ホルンの街周辺も例外ではない。実際ソロは、以前街外れの祠で守護水晶を見たことがある。青白い仄かな光を纏い、静かに輝く水晶が脳裏に浮かんだ。
「お兄さん、あれ……っ!」
と。
黄色い血を撒き散らしながら悶えていた魔物の傷が、みるみるうちに塞がっていく。目を見張る二人の前で魔物が大きく旋回し、狙いを定めた。それはソロでも、青年でもない。
ぽつんと道端に座り込み、べそをかいている子供である。
舌打ちする青年よりも早く、ソロが走り出した。