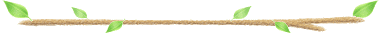
piece.01
始まりの街へ

エポナ村はとある地域の片隅に位置する、小さな村だ。妖精の一種であるグラスランナーの血を引く者達が集まり、平和に暮らしている。
春の祝祭の後片付けも終わろうかという今日、一人の妖精が旅に出ようとしていた。
「くれぐれも気を付けて行くんだぞ」
「帰ってきたら土産話をたくさん聞かせておくれよ」
「生水には気を付けるんだよ、旅先で体調崩すほど心細いことはないからねぇ」
「あぁ、今日は天気が良くて良かった。きっと女神様が祝福して下さってるんだな」
さして多くもない村人全員が広場に集い、心配や励ましの声をかけている。
その声援を浴びるのは、白に近い金髪を首の後ろで纏め、澄んだ水色の瞳を持つ少年。今日の主役たる彼は顔を赤くし、照れたり困ったりといった複雑な顔をしている。
「ソロ、マントの紐もちゃんと結んで」
「お母さん、遠足じゃないんですから……僕一人で出来ますよ」
「嘘おっしゃいな。つい最近まで蝶々結びもまともにできなかった子が」
村人達からどっと笑い声が上がる。母から指摘され、ソロは思わずにっこりと笑う母親から顔を背けた。僅かに尖った耳までが赤くなる。
とはいえ、何年も前から夢に見ていた日を迎える少年の胸は高鳴っていた。
ソロは今日、【水晶調律師】として旅に出る。
吟遊詩人であったという大好きな祖母──妖精族の先祖返りで性別は両性とされたそうだが、ソロは祖母だと思っている──コンチェルトは、ソロが小さい頃からよく昔体験した冒険を語って聞かせてくれた。ある時は冬の暖炉の傍で、またある時は眠れない夜の子守歌代わりに。
──いつか祖母のような詩人になり、世界を旅してみたい。
彼女の話に胸を躍らせる度、ソロは真剣に考えていた。音痴な自分でもできることはないか、必死に模索した。
最初は無謀だと笑っていた両親も、長年目標を変えない息子の姿勢に何か感じ入るものがあったらしい。ならば守護水晶を整備する職人になってはどうか、と勧めてくれたのは母親だ。
地域に差はあれど、魔物の脅威が人々の生活と隣り合わせに存在するこの世界で、魔物を退ける力を持った守護水晶の恩恵は大きい。需要のわりに数が少ないのも、水晶調律師が重宝される理由である。
今に伝わる守護水晶の修繕方法は様々だ。その中でも女神の世界創造を助けたとされる妖精族のそれは、楽器の演奏という伝統的なものだった。歌や音楽を愛し、それらを媒体に魔法を操る彼ららしい技法は、特に魔法に長けていないソロにも操ることができたのだ。
対して父親がソロに教えてくれたのは、野外活動を行う上で必要な知識である。自ら納得のいく材料を調達して、品物を作ることが多い前衛的な細工師。元々仕事に付いて歩く機会が多かったソロに、彼は改めて旅の心得を叩き込んだ。
かくして一通りの勉強を済ませたソロは、すっかり身支度を整えてここに立っていた。
身を包むのは今日のために母が仕立ててくれた楽師の衣装と、暖かく風よけになる深緑色のマント。頭には村の守護鳥シェラの羽の髪飾りを挿していた。腰のベルトに吊ったホルダーには、祖母が愛用していた横笛が納まっている。
両肩で背負う革袋の中には携帯食糧に寝袋や薬草、火打石、簡単な着替えなどが一通り揃っていて、まさに準備は万端だ。
──だが先日の祭で散々語り明かしたというのに、出発当日も村人達はこの騒ぎようである。こんなことでは、村を出る前に日が暮れてしまいそうだ。
ソロは一向に解放してくれる気配のない村人達を見回し、目の前の母に目配せを送った。母は頷き、目を細めて少しだけ淋しそうな顔を見せる。
「いってらっしゃい、ソロ」
「……はい!」
直後、ソロはそこから駆け出した。
「あっ! ソロ坊が逃げたぞ!」
「おい、もうちょっとまっ」
「あらあら、貴方達のもうちょっとって何時間ですか?」
唐突な主役の逃亡。ざわつく村人達に、母が笑いながら指摘している声が聞こえた。
「そんなに惜しまなくてもいいじゃありませんか。可愛い子には旅をさせよ、ですわ」
「(……ありがとうございます、お母さん)」
ちくりとした痛みが心を刺す。ソロは走りながら後ろを振り返り、大きく手を振った。
「いってきますっ!」
ここだけの話。
送り出されなければ発てそうにない、というのは少年自身にも言えることだった。ソロは暖かいこの村が、大好きだからだ。
村の門を出てすぐの場所に、朝一番で隣街へ向かう荷馬車が待ってくれている。まず隣街に立ち寄って、細工屋で働いている父親に挨拶して行くつもりだった。
大きな期待と不安、それと母にさえ言えなかった秘密がひとつ。
色々なものを胸に抱えて、ごくごく普通の少年は最初の一歩を踏み出した。